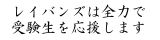秋のリーグは、初戦から3連敗の後、3連勝。
第3戦目の京都大学戦ではエースQB#12尾崎が腕を骨折し、途中退場。強力オフェンスの京都大学を前に記録的大敗を喫した。
第4戦目の関西大学戦は、大敗した京都大学戦後の試合で、関西大学サイドは神戸大学オフェンスはランしかないとの読みで対応してきたが、その裏をかいた攻撃が奏功し、ラン・パスが決まって大勝。
第6戦目の岡山大学戦では、神戸陣7ヤードまで攻められていたが、岡山大学がファンブルしたボールをリカバーし、神戸大学攻撃に。京都大学戦で負傷した#12尾崎の代役を務めた2回生QB#11今中が93ヤードを独走し、残り1分を切っての大逆転勝利を果たした。
最終大阪体育大学戦は神戸大学教養部(現国際文化学部)グランドで行われた。勝ち越しがかかった一戦だったが、ホームの利を生かせずに敗れ、3勝4敗同率4位という成績に終わった。
(レイバンズ30周年記念誌より抜粋)
チームの主力である多くの卒業生を送り出し、シーズン終了後間もなく森ヘッドコーチから手渡された1冊の洋書。
「パスは捨てプレー」から一転して、パス攻撃を中心としたオフェンスの組み立てを考えよとの話であった。
終了したばかりのシーズンでは、パスのたびに1部リーグの巨大なディフェンスラインに追いまわされた後だけに良い夢は見られなかった。
不安を抱えて迎えた81年度シーズン。
シーズン最初の関西学院大学戦の結果は敗戦であったものの、確かなものが感じられた。
その後も、開幕から4連敗ではあったが、確実に1部リーグのスピードがチーム全体が馴染んでいた。第5戦の立命館大学戦ではオプションを交えたラン攻撃、ゾーンの切れ目へのパス攻撃が機能し、ディフェンスもワシントン大学のシステムとスカウティングの成果をマッチングさせることができ、1部リーグ初勝利をあげる事ができた。
最終戦の同志社大学戦にも勝利し、2勝5敗、5位の結果を収めた。
(レイバンズ30周年記念誌より抜粋)
前年に1部リーグ昇格を果たし、意気揚々と望んだ春の初戦は、関西学生フットボールの聖地・西宮球技場での同志社大学戦であった。
それに始まり、秋のリーグ、京都大学、関西大学、同志社大学、大阪体育大学、近畿大学、立命館大学、関西学院大学。昇格の原動力となった4回生を中心に完成度の高いプロIからのトリプルオプション、ワシントン大学から取り入れた画期的なディフェンスシステムは効果的に機能するはずであった。
しかし、1部リーグのスピード、試合運びについていけず、近畿大学や関西学院大学には善戦できたものの、関西大学、京都大学にはこれでもかとやられる結果となった。
結局、初の1部リーグ戦は全敗で入れ替え戦にまわることになったが、1部リーグで揉まれたことが幸いし、相手チームを寄せ付けずに勝利して次のシーズンに夢をつないだ。
(レイバンズ30周年記念誌より抜粋)
当時の3回生が質・量ともにチームを支え、2回生以降も数多くのタレントが活躍するようになっていた79年シーズン。
チームのメンバー数も50名以上になり、2部リーグではトップクラスの実力を具え、1部リーグ昇格を狙えるポジションにあった。
リーグ戦最大の関門は、前年1部から降格してきた甲南大学との最終第5戦。
最終戦でブロック優勝をかけて直接対決するまでの彼らの戦績は4勝0敗、平均スコアは得点61点、失点0点でデータ上はRAVENSを遥かに上回っていた。
当時はパソコンなどもなく、手書きのマトリクスと電卓を駆使して、敵の攻撃パターンを分析し、相手エースランナーのランをことごとく止め、結果、34対7の圧勝であった。
勢いにのったRAVENSは入れ替え戦出場権も手に入れ、万博競技場で行われた1部リーグ7位の大阪経済大学との入れ替え戦は見事勝利を得、1部リーグ昇格を果たした。
(レイバンズ30周年記念誌より抜粋)
前年の入れ替え戦をかけたトーナメントでの敗北から翌年の1部リーグ昇格に至る草創期における変革・変動のシーズン。
まず、人材面での充実があげられる。
2部リーグでは突出した部員数を誇り、また、77年シーズンに辛酸をなめたメンバーが成長するだけでなく、新入生を迎えて選手層が格段に厚くなった。
それに伴い、戦術も変化していった。
さらにこの年の春、初めて京都大学と練習試合を行うことができた。
京都大学にとっては新人戦の相手に選んだ、という程度の試合ではあったが、京都大学グランドには所狭しとRAVENSを応援する人が集まった。
当時RAVENSは「第二の京大」と一部のマスコミに持て囃されていたが、やはり1部リーグとは違うという認識を新たにし、「神大RAVENS」としての確固たる地位を得たいという気持ちは大きく膨らんでいった。
78年シーズンは、ブロック2位という成績に終わったが、チーム全員が一丸となり、1部リーグ昇格を成し遂げる翌シーズンの「プロローグ」となったシーズンであったと言えるだろう。
(レイバンズ30周年記念誌より抜粋)
「アメリカンフットボール部を創りたい、同志は4月26日、教養部・食堂前に集合」。この言葉から、RAVENSの歴史は始まる。
その年、入学したばかりの松田(充啓)は、アメフト部を創るべく、教養部(現国際文化学部)の全教室の黒板にこの言葉を書いて回った。
運命の4月26日。
食堂前には、一人、また一人と、誰も連れ立ってくる様子は無く、同志たちが集まってきた。はじめは同好会としてのスタートだった。
松田(純一)を除く全員が未経験者、見るからにアスリートという猛者がいるわけでもない、手探り状態での幕開け。ひたすらダミーを打ち、土にまみれ、ボールを追いかけ汗する毎日。そんな手作りのチームではあったが、純粋にフットボールを楽しむ気持ちとその喜びはRAVENSの歴史の中でも一番だったと言えるだろう。
創部されたばかりのチームにとって幸運だったことは、経験者の松田(純一)がチームに加わっていたこと。体育教官の綿貫先生が顧問となり、部室の確保、カメラ・ビデオ等の備品が使用できたこと。教養部のグランドが使用できたこと。そして、他校でも創部が相次いだ時期であったこと。こういった幸運を背景にRAVENSの土台は作られ、一橋大学OB長井啓氏のコーチ就任で花開き、創部2年、わずか20数名でのブロック優勝を果たした。
「RAVENS」の命名に際して念じたことは「甲子園へ」。その思いは以後のチームに絶えることなく伝わっている。
(レイバンズ30周年記念誌より抜粋)